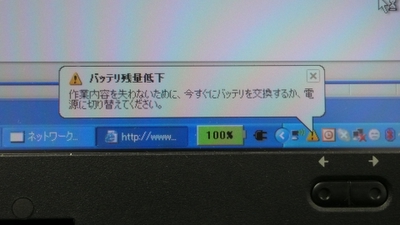独立したら、最初におほえなければならないことのひとつに、見積の基準というものがある。
発注者は、この見積もりを何社からも取って、一番条件がよい業者を選択するのであるから、就職活動にたとえれば履歴書のようなものである。いい加減であってはならない。
僕らのいるゲーム業界は、かつてバブル隆盛の業界だった名残で、一人月90万円とか100万円、というバブリーな見積単価がいまだにまかり通っている。開発の受託をする際は、この金額に作業年月を掛け合わせて受託金額を計算するわけである。それが結構な金額になってしまうわけで、コスト競争の激しい映像制作の世界に身をおく知人はこれを羨ましがりつつ、そして憂いている。
よい組織というのは、一見担当者が一人にみえてもその後ろに多くのスタッフに支えられた付加価値が用意されているものだ。作業を受けおった側では、実際に本人に給与として払われているのは請求単価の3-4割ぐらいがいいとこで、残りはそのサービスのためのコストとして割り当てている。担当者から見るとピンはねされているようだが、実は安定した負荷分散の体制がここにはある。
ところが、そういう表面ばかりを見ている独立ビギナーは勘違いしてしまいがちだ。ただただ現象面だけをみて、猫も杓子も、ただの人も、一つ覚えのように一人月100万、という数字を見積もり単価として出してしまう傾向がある。ゲーム以外だとウェブサイトのフリーランス関連にもこの傾向は強いようである。たったひとりで仕事を納品した錯覚に陥りやすいのがIT関連の特徴なのかもしれない。
一つの仕事をおえたとき、クライアントから「あそこにお願いするのはもうやめておこう」といわれるケースというのは、だいたいその原因として、こういった個人企業の見切り発車の見積もりがある。単価が高いことは仕事を受ける側としてはなにかと都合がいいし、なににもまして気分がいい。でも、しかし、ちょっとしたつまづきでぼろが出ることがある。それはミスなどで個人では事態収拾できないような状態に直面したときである。個人というのはじつにもろいものだ。そのバックアップがあるのとないのでは大きく違いがある。
本当にクライアントとよい関係を続けるには、自分がたとえ法人登記してあってとしても、実質は個人であること、そしてそれに見合った見積単価を採用すること、が重要である。実績がたまってきてから単価を上げてゆく相談はあとからいくらでもできるから。それが日本という国である。
そのあたりをもうすこしくわしく説明することにしよう。
企業の担当者というのは、安い高いを感情で判断するものではない。大企業ほど、そうである。
じゃ何を意識しているかというと、確実性というやつである。
計画が当初の納期と品質、そいて予算どおりに進めばそれが一番よいのである。途中で受け側の理由でがちゃがちゃと変更になることがもっとも迷惑なのである。
だから業務を発注する側からみると、この100万円というのはプログラミングなどの費用だけを期待している値段ではないのだが、それを独立ビギナーはなかなか気がつかない。
そもそもこんな高い人件費単価がそこそこのプログラマーの単価としても許されるのは、ここにマネジメントの費用と、リスク準備金、そして営業コストといったものが入っているからである。普段は目に見えないものだが、水や空気のようなもので、ないと相当困ることがある。
マネジメント費用というのは何かというと、その人材を監督する側のコストである。
受託というのは、作業者が仕事をやっているように見えるけれども、実際はその背景に監督している者がいて、いわば企業という監督責任母体があるから安心して発注できるのである。突然出社しなくなった派遣社員を自宅まで様子を見に行く、なんてばかばかしい行為を派遣会社の監督者は日々やっているわけで、発注側はそのあたりをなにもしなくてもいい。その付加価値が実に大きいわけで。
リスク準備金というのは、受託した仕事を見積もりどおりに完成させることができなかったときの企業責任である。自分の勘違いで堂々と遅れを出して、「いった、いわない」でまんまと一人月100万円レートで請求するというのは、かなりの勘違い野郎というレッテルを貼られる。
正式な見積書にはたくさんの捺印がなされているが、それはすなわち、「この金額できっちりと収めて見せます」という保証の意味がある。保証をする以上、リスクが発生するわけで、それを上のせして単価を出している。もし担当社員の能力不足や怠慢で遅れた場合は企業がそれほかぶるのだから当然といえば当然だ。
そして営業コスト。これが実はとても重要である。
発注する側というのは、自分のオフィスにのほほんと座ってあれこれと指示を出すことができれば一番効率がいい。それをきっちりと受け止めて担当者に伝えるのが営業マンで、いった言わないがないようにドキュメントを揃えたり、担当者に直接いいにくいことを、クライアントから快くきいてもって帰るのも営業マンである。クライアントが来社して打ち合わせをする、なんてこともあるわけで、そのためのスペースを準備するのも営業コストである。
こういったサービスがクライアントにとってはとても大きい。そもそも仕事を外注するクライアントというのは、困っているから外注する。いわば体力が落ちた患者みたいなもので助けて欲しいのである。それをちゃんと助けるから医者は偉いわけで、トラぶった時に患者に面倒な仕事をおっかぶせるのであれば単価基準は完全に変化すべきである。
つまり予定どおりにきっちりとプロジェクトを遂行させるための保険が企業のサービス料であって、そこをすっぱりと落としていながら「同レベルのサービスだから」と言い張るのは、実はとても子供っぽいことと見られてしまう。
数年前の話であるが、特殊な業務をアウトソースする際、いくつかの候補会社とコンタクトした。その一社で、規模は数名だが、みな腕がよく仕事が速い、という会社のエンジニアの方が来訪したことがある。
そのときは、担当エンジニア本人がたった一人で来た。一人月150万円、だという。
単価は高いが、腕がよくスピードが早いのでトータルでは安い、というという前評判を聞いていたので、僕も好感をもって会議をすることができた。だらだらとした会議とちがって、じつによい内容だった。本当のスペシャリストというのは、瞬間最大風速がおそろしく早くてしかも確実だ。組織というより天才ハッカー集団、といった雰囲気に感じた。
おそらく、彼に仕事をお願いしたならば、すごくスピーディーに業務は進むに違いない。だが、もし彼が交通事故で入院したら、ということを考えなければならないのがプロジェクトというものである。もっと具体的にいうと、彼が入院したときに、それを待つであろうメンバーは10名近くになるから、ロスするコストは月150万円とは比べ物にならない。金なんか返さなくてもいいから至急バックアップ体制を組んでくれとなる。その準備はあるのか、不都合が発生したときに誰が社内で開発途中の案件を動かしてくれるのか・・。そう考えると、発注することができなかった。残念だったがいたしかたなかった。
独立したての頃というのは、とかく鼻息が荒いものである。
大企業には負けないぞ、と屋号だけ会社を名乗っている「実質個人」もこの業界には多い。
でも本当に重要なことは、会社を名乗ることではなく、「本当の組織になっているか、それとも実質は個人か」を潔くはっきりさせることだと思う。携帯電話でしか連絡がとれない人、秘書や伝言してくれる人がおらず、ちょっとし連絡をとるにも手間がかかる人。そういう人には、ちいさくないマネジメント負担が発注側の担当者にもどっしりとよりかかってくることになる。そういう目に見えないコストとリスクはビギナーの眼中には入ってこないものだ。
「出来さえよければいいじゃないか」そう考えて生きてきた僕は、かつてそれで大失敗したことがある。僕とは違いそのバックアップのための投資をした人々は、いまでは優れた組織を持つにいたっている。
自分は組織か、それとも個人か。潔くそこに準じることはチームワークへの貢献であり、社会と共存してゆくための最大の秘訣ではないかと思う。